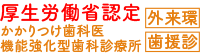致知感想文
皆さまこんにちは。鴨居歯科医院 歯科衛生士の髙木さなえです。2月号の感想文を投稿致します。
62頁 二〇五〇年 富国有徳の国にするために
「二〇五〇年、日本は再び甦る兆しを見せるであろう。 二〇五〇年になったら列強は日本の底力を認めざるを得なくなるであろう」 哲学者・森信三師の晩年のこの言葉を現実のものにして、日本を世界が憧れる富国有徳の国にするためにはどうするべきか。 この世の営みには必ず波があり、下りの波もあれば上りの波もある。現状の日本の悪い面が目につく一方で、「致知」を読んでがんばっている会社や、学校が増えつつあることや、日本は地震や台風、津波、洪水などの常襲地で、住むのには非常に条件の悪い国ではあるが、太古の昔から人々は限られた土地でお互いに助け合い、共に試練を乗り越えながら無私と忍耐、勇気や協力といった人間としての美質を厳しい環境の中で育んできた。 自然には人間ごときには太刀打ちできないすごい力があることを認めて、神社の前で頭を下げる謙虚さは日本人としての強みではないか。そして、協力する力、チームで頑張る力、会社にしろ家庭にしろスポーツにしろ、複数の人間が集まった時に力を発揮する、それが日本人らしさ、日本人らしい姿ではないか。
謙虚で誠実であることも日本人の美質で、石門心学の祖である石田梅岩は、商人の道を説い、梅岩が強調したのが精神的価値についてです。 金銭的満足を越える精神的喜びは、例えば反物を二つに分ける時に、織りの良い方を相手に与える。それで損をするかというと決してそんなことはなく、相手によいものを与えたという満足が得られる。その満足は金銭的満足より遥かに尊い。京セラを創業し、JALの再建を果たした稲盛和夫氏も勤勉性の大切さの言葉を数々残されています。 「一所懸命働く中で自分の魂を磨き、生まれた時より少しでも美しい魂で生を終えていくことが人生の目的だ」 稲盛先生の生き方を私たちは更に学び、一人ひとりが自分の仕事に一所懸命に取り組み、心を磨いていくことを忘れずにいたいと思います。 自分の仕事を本気で取り組むと、楽しささえ感じることがあります。「楽」と「楽しむ」は意味合いが全く違います。楽をしようはだめですが、楽しんでいると楽になり、楽しみが増える(仕事ができるようになると)どんどん高みを増していく…。働くことの楽しさをみつけることは、自己を高めていく修行、覚りへの営みなのだと、多くの人が気づくことで、日本は再起への道へ進めるのだと思います。
日本が富国有徳・日本の美質に世界が注目し、自ずと日本を手本とするようになるには、日本古来の精神に立ち返ること。幸せに生きるということや、人生の喜びとは、周りの人たちを幸せにするという精神性。無私、忍耐といった特質を発揮するためにも、取り組むべき課題は教育ではないか。そのためには、教師の質を上げていく。それによって、教師になりたいという子どもが増え、教師の質も上がっていく。こうした良いスパイラルを回していくことで社会全体が良くなっていく。
二宮尊徳は「積小為大」を説き、小さなことでもコツコツ積み上げていくことによって高みに登る、すなわち国民がよい方向にベクトルを合わせると、国もよい方向へ向かうということを示唆している。一人ひとりが自分を高め、一隅を照らしていくことによって富国有徳の国づくりが実現できる。同時に私たち大人は読書文化の復興を目指す。本に向き合わない限り、正しい知識や教養、情緒、日本人としての美質は身につかない。自身を磨く上で読書は重要だと学びました。 今年も頂ける毎月の致知を読むことと、様々な本も読み学んでいきたいです。
最後までお読みいただきありがとうございました!